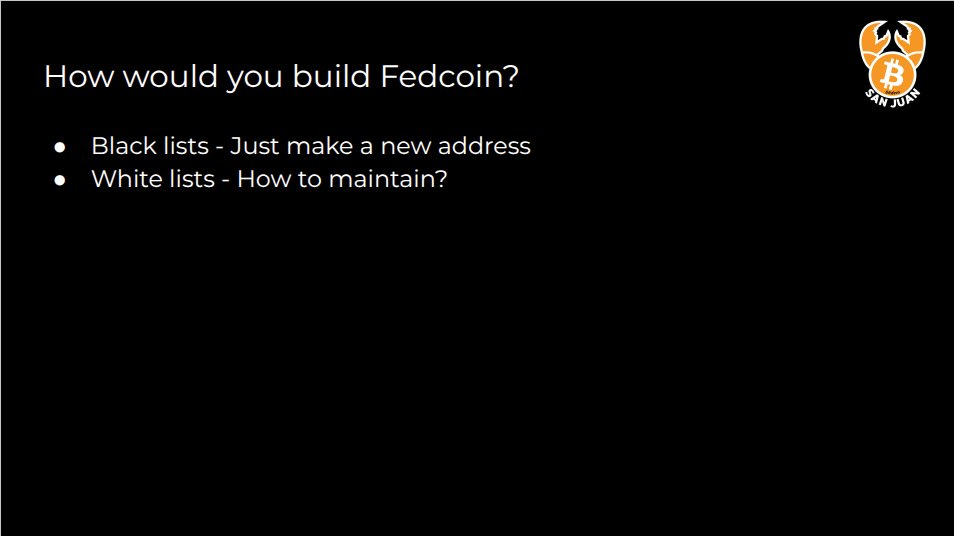「再帰的なCovenants」とビットコインの進化リスク / アダムバックが語る「ビットコインの未来と企業財務の再構築」
本日取り上げるのは、【Recursive Covenants(再帰的なコベナント)】についてです。
いきなりですが、「ビットコインを通貨ではなく、プログラマブルな台帳として拡張する方向性」について、みなさんはどう思われますか?
これは単なる技術的な進化ではなく、ビットコインの本質――つまり「何を守り、何を許容するのか」という思想的選択を迫る問題かもしれません。
たとえば現在、OP_RETURNのデータ埋め込み制限(上限83バイト)を撤廃しようという議論が持ち上がっているかと思います。
(※過去に、Pro向けニュースレターでも取り上げました「前々回」「前回」)
一方、Covenantsとは、ビットコインのUTXO(未使用出力)に対して「どのように使うか」を制限するスクリプトです。
たとえば「このコインは次にこのアドレスにしか送れない」といった制限をした場合。
そして、それが再帰的(Recursive)に適用されてしまう場合、「コインの将来の使い道」までが永続的かつ自動的に制限される可能性が出てきます。
CovenantsとOP_RETURNは性質こそ異なるものの、ビットコインの機能を「通貨」から「制御可能なデータ構造」へとシフトさせるという意味では、
広い範囲で同じ方向を向いているのかもしれません。
この点において、多くの開発者が抱く強い懸念は、技術の話ではなく「価値観の話」でもあります。
こんにちは!yutaro です。
さっそくですが「BTCインサイト」本日のトピックスはこちら:
「ファンジビリティ(代替可能性)はなぜ重要か」──再帰的Covenantsとビットコインの進化リスク
1兆ドル企業の戦略的選択肢──アダムバックが語る「ビットコインの未来と企業財務の再構築」
【スポンサー】Jade Plus By Blockstreamのご紹介
BTCインサイトは、ビットコイン保有者向けの究極のハードウェアウォレットJade Plusに支援されています。
Jade PlusはBlockstreamがプロデュースする最新ハードウェアウォレットで、以下のような優れた機能や特徴を持っています。
オフライン環境でのエアギャップ送金や、ファームウェアのアップデートに対応。外部からの攻撃を完全に遮断。
仮想セキュアエレメントを採用し、ハードウェアウォレットが盗難されても物理的に秘密鍵を抽出するはできません。
正規品デバイスチェック機能を搭載し、ハードウェアの改造やサプライチェーン攻撃を防ぎます。
最新最高のビットコインセキュリティに加え、美しいデザインとUXを兼ね備えています。
Jade Plusは、BlockstreamのパートナーでもあるDiamond Handsが運営する Lightning Base オンラインショプで購入できます。
ビットコイン/ライトニング決済割引と国内匿名配送もご活用ください。
DH Magazine Pro に参加しませんか?
月7ドルで【DH Magazine Pro】に参加して、ビットコインの最前線と世界のトレンドを楽しみつつ、Diamond Handsの活動を支援していただける方を募集中です!
詳細は以下のPro版の内容紹介記事をご確認ください。
「ファンジビリティ(代替可能性)はなぜ重要か」──再帰的なCovenantsとビットコインの進化リスク
(※本記事は、Hannah Rosenberg(@hmichellerose)氏によるX投稿をもとに要約・編集したものです)
ビットコインにとっての「価値観」の違い
最近、Hannah氏は「Recursive Covenants(再帰的なコベナント)」に強い関心を持っているそうです。
※補足:Recursive Covenantsとは、「このビットコインは次にどこに送るか」を決めておけるルールのことです。しかもそのルールがずっと続く(再帰的)ことで、将来の使い道までしばられてしまう可能性があります。
ですが、技術的なことよりも、議論で本当に問題になるのは「ビットコインをどう考えるか」という価値観の違いだと気づいたのだとか。
彼女は「ビットコインはお金として使うべきもの」と考えています。
2017年には「分散性」がビットコインの絶対的な価値として語られていました。
では、「ファンジビリティ(代替可能性)」はどうでしょうか?
それもお金としての性質には欠かせないものです。
Recursive Covenantsが生むリスク
Recursive CovenantsがUTXOに適用されると、ビットコインのファンジビリティが損なわれると、Rosenberg氏は言います。
つまり、「そのコインが次にどう使われるか」をずっと縛ってしまうのです。
制限には3つのレベルがあります:
プロトコルレベル(もっとも深刻)
ネットワークレベル
経済/法律レベル
たとえば「2-of-2マルチシグ」よりも、プロトコルで強制される制限の方が、はるかに大きな影響を持ちます。
とはいえ、ファンジビリティが少し崩れたからといって、すぐにビットコインが使えなくなるわけではありません。
「完全でなくても使えるかもしれない」という議論もあります。
悪用される可能性と現実的なリスク
たとえばRecursive Covenantsを使えば、「ホワイトリストに載っていないアドレスには送金できない」というような仕組みも理論上は作れます。
ですが実際は、それを作り替えることがとても難しいのです。
中央銀行がFedcoin(政府発行コイン)のような通貨を運用しようとしても、Recursive Covenantsのように変更しにくい仕組みでは、
逆説的ではありますが、実は意外と不便なのかもしれません。
また、Rosenberg氏が警戒する最大のリスクは、技術そのものではありません。
多くの人がビットコインを預けている大規模カストディアン(取引所など)の存在
これがプロトコルレベルの制限と結びつくと、ファンジビリティへの攻撃の入り口になる可能性
だから、彼女はこう言います。
「セルフカストディ(自分で保管すること)がもっと当たり前になれば、このリスクは減らせます」
ビットコインにおけるファンジビリティとは?
「ファンジビリティ(代替可能性)」とは、すべてのビットコインが同じ価値を持っていることです。
ですが、それは完全に“同じ”という意味でしょうか?
たとえば:
米ドル紙幣にはシリアル番号があります
ビットコインには取引履歴があります
記念硬貨は他の硬貨と違って特別に扱われます
こうした事例から考えると、ファンジビリティは「完璧に同じ」か「そうでないか」の二択ではなく、
連続的な幅(スペクトラム)として理解した方が現実に近いといえます。
Recursive Covenantsの本当の危険性
本当に危ないのは「再帰的であること」そのものではなく、どのような制限が作られてしまうかです。
現在提案されている主なOpcode:
OP_CTV(CheckTemplateVerify)
OP_CSFS(CheckSigFromStack)
OP_CAT(Concatenate)
この中でも、OP_CATのように複雑で予測しにくい制限が可能になるコードには注意が必要です。
守るべきものは何か?
Rosenberg氏は、「ビットコインにおいて守るべきはのは何か?」と問いかけます:
ビットコインの上限(2100万枚)?
非中央集権性?
ファンジビリティ?
これらのうち、何を“本質”と考えるかによって、支持すべきアップグレードは変わってくるのです。
(※原文はコチラ)
今は「慎重に進む」とき
Rosenberg氏の結論はシンプルです:
「私たちはまだ答えを知らない。だから、思慮深い推測を重ねることが求められている」
そして現時点での彼女のスタンスは以下の通り:
CTV → 採用してよい(YES)
CSFS → 検討の余地あり(Maybe)
CAT → まだ導入すべきでない(Hold)
新しい技術を取り入れるときは、その影響をよく考えながら、一歩ずつ進める必要があるのかもしれません。
1兆ドル企業の戦略的選択肢──アダムバックが語る「ビットコインの未来と企業財務の再構築」
(※本記事は、The Big Whaleに掲載されたRaphaël BlochによるBlockstream CEO アダム・バック氏のインタビューをもとに要約・編集したものです)
ビットコインの二面性:「支払い手段」と「価値の保存」
アダムバック氏は、「ビットコインの本質的な価値は、富の保存手段であると同時に、金融包摂を実現する支払いネットワークとしての機能にある」と語る。
OECDによれば、世界の労働人口の約50%が銀行口座を持たず、現金払いが主流。
ビットコインは、こうした人々に経済参加の機会を提供します。
論より証拠ですが、発展途上国では”Lightning Network”を通じた日常決済が、浸透しつつあります。
一方、先進国では投資資産としての側面が強く、価格形成にも大きく寄与しているのです。
実際、決済に使われるビットコインはすぐに法定通貨へ換金されるため、価格への影響は限定的だが、長期保有(HODL)の投資は価格を安定的に押し上げています。
ETF承認と企業導入がもたらす正当性
近年、スポットETFの承認などを受け、金融機関や企業の間でビットコインの採用が加速しています。
伝統的な金融機関にとって、以前はリスク資産と見なされていたビットコインが、今や分散投資の選択肢として浮上している。
Blockstreamでも、2023年から資産の一部をビットコインで保有しはじめました。
ご存じの通り、米MicroStrategy(ストラテジー)の事例が象徴的です。
コロナ禍の金融緩和により資産価格が急騰、現金や国債保有の実質価値が減少し、これに対抗する形で、企業財務にビットコインを組み込む動きが広がりました。
財務戦略としてのビットコイン
アダムバック氏は「ビットコインはマズローの欲求階層における基本的ニーズに近い」と語ります。
法定通貨のように貯蓄の購買力が維持できなければ、努力の意味も未来への計画も成立しないからです。
たとえば、ある企業は5億ドルのキャッシュを保有していたが、年間10%ずつ価値が減少していると認識しました。
これを機に個人としてビットコインを購入し、最終的に企業でも導入を決断したのです。
債券発行によるレバレッジ運用なども可能となり、個人投資家では享受できない戦略的な柔軟性を獲得しました。
注目すべきは、これらの企業がビットコインの保有数だけでなく、1株あたりのビットコイン量(bitcoins per share)を増加させていること。
これは株主にとって非常に魅力的な指標です。
新たな評価モデルと財務強化
The Blockchain Groupのように、ビットコインを担保とした転換社債モデルを採用する企業も登場しています。
価格が一定以下でも返済可能な構造を持ち、価格変動リスクを巧みに回避しています。
財務体質の強化は、オペレーションとの両立を阻害するどころか、むしろ資源と柔軟性をもたらすのです。
今後5〜10年で覇権を握る企業は、財務戦略の段階でビットコインを選択した企業である可能性が高いでしょう。
仮に、ビットコインの年平均成長率(CAGR)が60%から20%、10%へと鈍化しても、最も多くビットコインを保有する企業が有利なのは変わりません。
最後に:マイニング、報酬、そして生存性
現在のマイナー収益の多くは新規発行分から得られていますが、過去には手数料収入が高騰した時期もありました。
ビットコインのネットワークを支えようとするインセンティブは今後も維持され、最終的にはホルダーたちがその生存を保証していくことになるはずです。
(※原文はコチラ)
バランスシートが“攻め”になる時代
ビットコインを財務戦略に取り入れる企業が増えているのは、「余剰資金の保全」だけでなく、「市場における戦略的優位」を狙っているからです。
これは、過去の「工場を増やす」「広告を打つ」よりも、遥かに強力なレバレッジのかけ方として一般化するかもしれません。
成長が鈍化した企業ほど、財務面での再起動が必要です(善し悪しは別にして)。
長期で見れば、先にビットコインを積んだ企業にこそ、優位性があるのかもしれませんね。
🌀 その他のトピックス
⚡ 役立つ記事や特集
💎 DH関連リンク集 🙌
気に入っていただけましたか?
月7ドルで【DH Magazine Pro】に参加して、ビットコインの最前線と世界のトレンドを楽しみつつ、Diamond Handsの活動を支援していただける方を募集中です!
詳細は以下のPro版の内容紹介記事をご確認ください。
https://diamondhandscommunity.substack.com/p/dh-magazine-pro