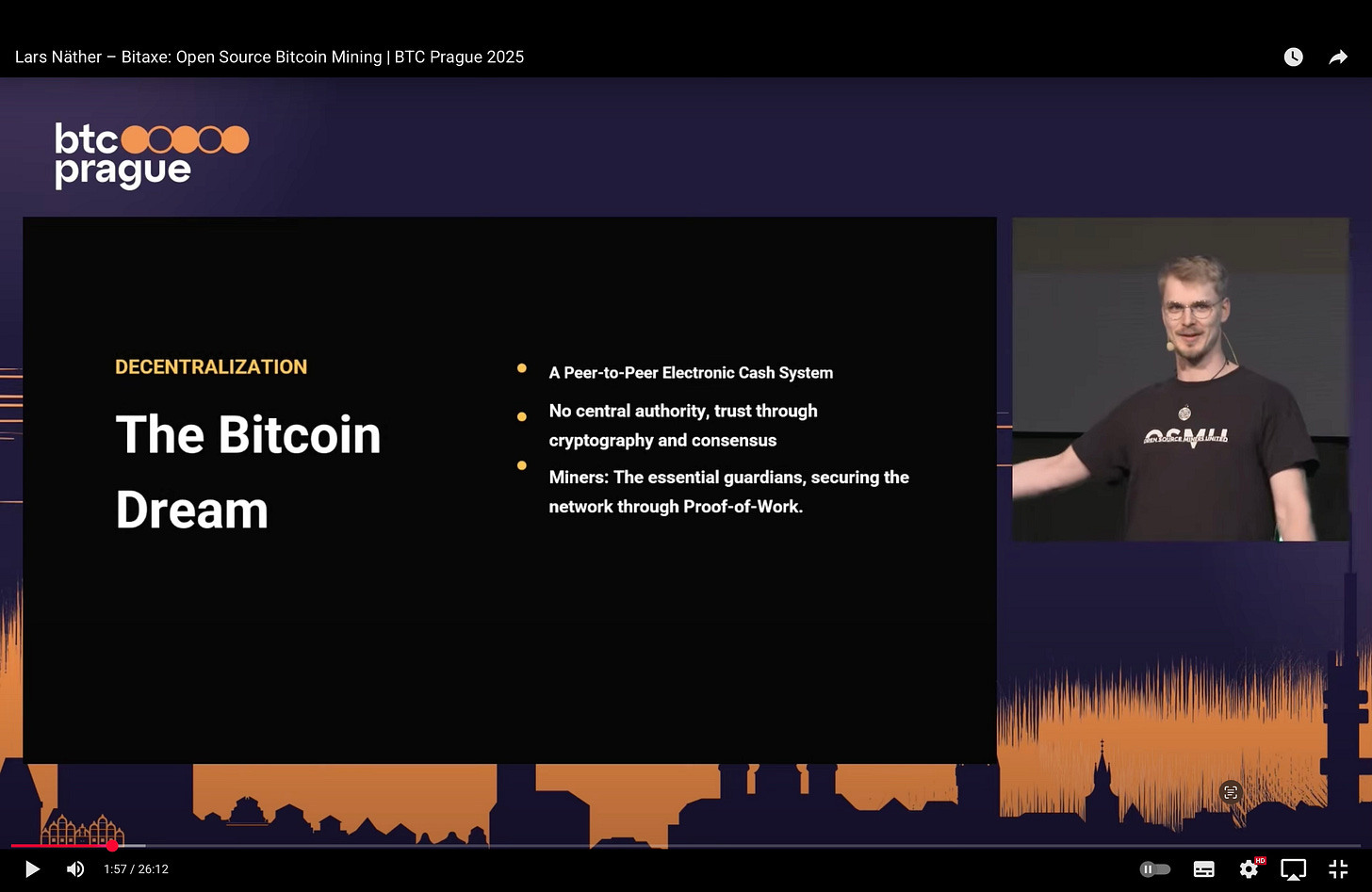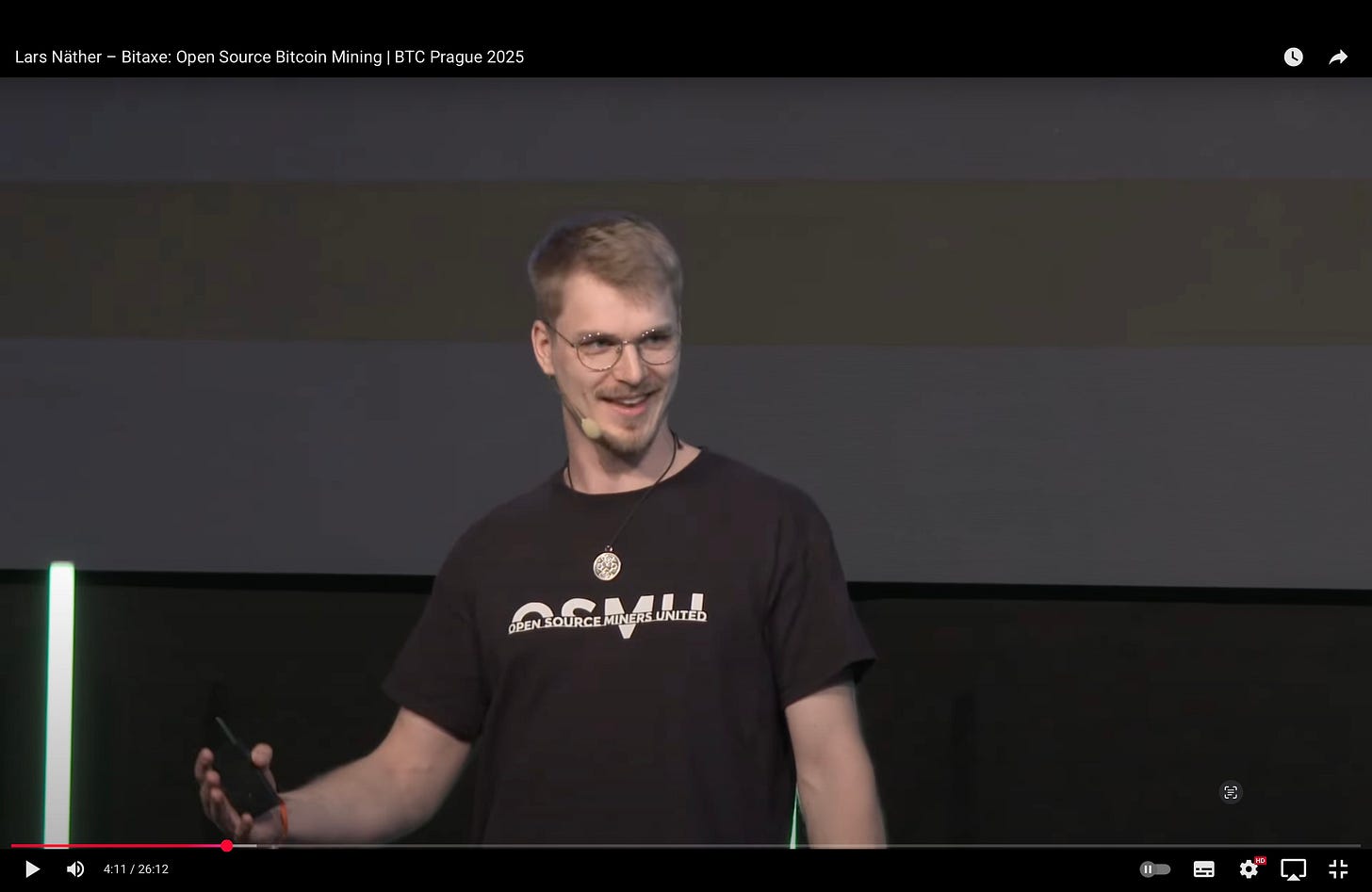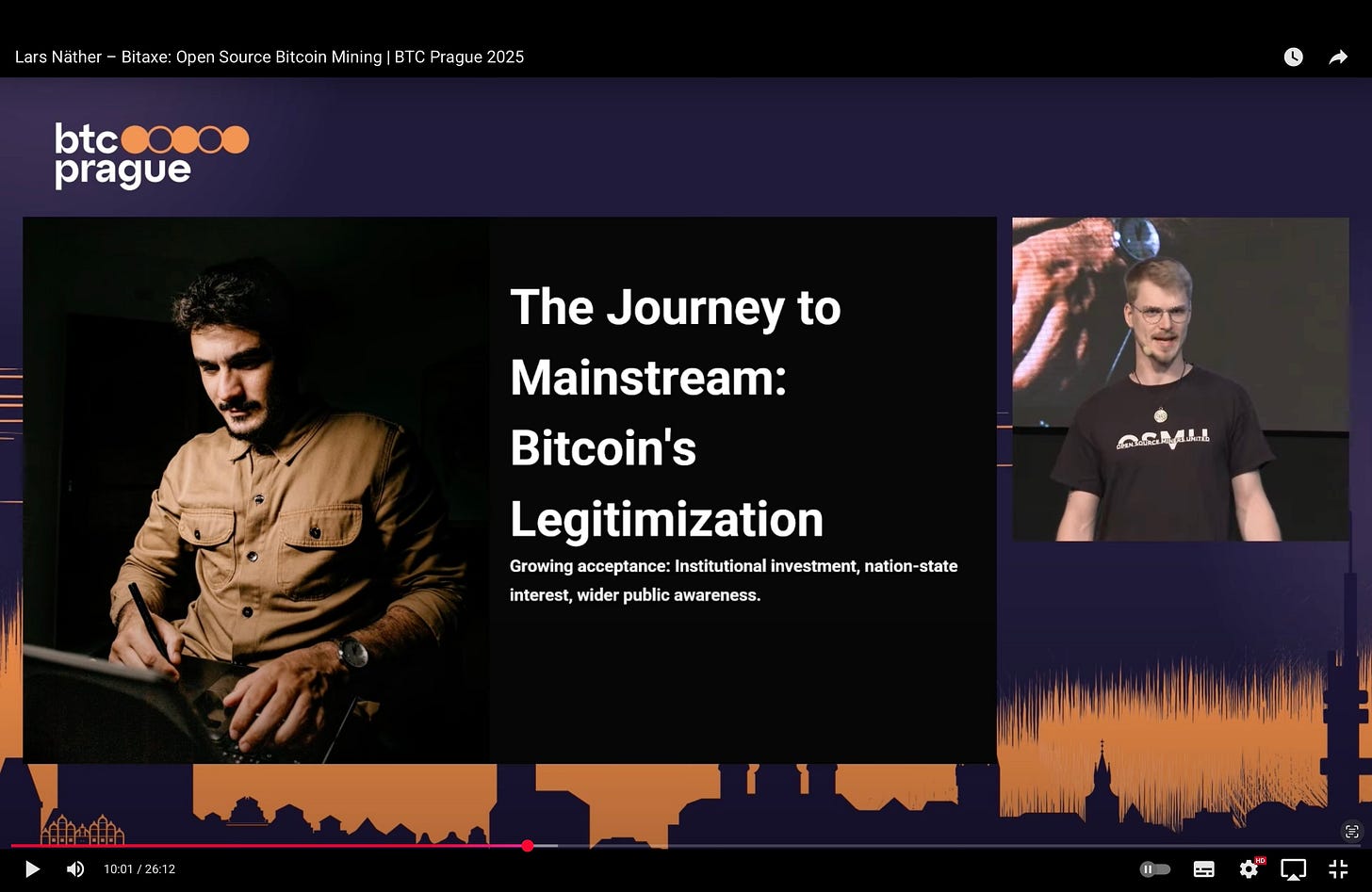ビットコインの夢を守るために:Bitaxe オープンソース・マイニングの挑戦
ここに来られてうれしく思います。ええと、僕はこういうトークを始めるとき、たいてい皆さんに一つ質問をします。これがあなたにとって初めてのカンファレンスかもしれないし、2回目、3回目かもしれません。でも、自分に問いかけてみてください。カンファレンスで何を学びましたか?何を見ましたか?
ノードの扱い方、トランザクションの作り方、プライバシーを守り、オプセック(運用上のセキュリティ)を可能な限り高める方法──そういうことを説明する人たちはいます。でも、マイニングについてはどうでしょう?何か学びましたか?
この会場(BTCPrague 2025)の通り沿いには、あなたのマイニングマシンをホスティングしてくれるというブースや、次のマイニング機器を売っているブースがずらりと並んでいるのを見かけたはずです。でも、その中身は?どう動くのか?どこに欠点があるのか?そして特に、彼らが語らないことは何なのか?
今日は、そうしたトピック──とりわけビットコインにとって非常に重要な「マイニングの分散化」──について話したいと思います。僕自身、このテーマに強い関心があり、なぜマイニングの分散化が必要なのか、そして現在の状況がどうなっているのかをお伝えします。僕は Clue(クルー)といい、Bitaxeの開発者の一人です。聞いたことがある人もいるかもしれませんし、ない人もいるでしょう。知らなくても大丈夫。これからお見せします。
こんにちは!yutaro です。
本日のPro向け「BTCインサイト」では、オープンソース・ソロマイニング “Bitaxe(ビテックス)”の開発者の一人 クルー氏の講演を翻訳・編集してお届けします。
このニュースレターの読者の中には Bitaxe ファンや保有者も多いと思いますが、今回の講演はマイニングの分散化について改めて考えさせられる内容でした。
ビットコインが与える夢
まずは少し背景から。ビットコインをご存じない方にビットコインを紹介したい……と言いたいところですが、知らないと言われたらさすがに驚きますね。ビットコインには「夢」があります。ビットコインは人々に、分散化という夢──仲介者がいないP2P(ピアツーピア)の電子キャッシュシステムで、誰にもコントロールされない──という夢を与えます。これこそが、僕たちがビットコインに抱く夢です。
そして素晴らしいのは、2009年にビットコインは MIT ライセンスのもとで公開されたことです。ライセンスの細かい話は知らなくても構いませんが、当時は「誰でも読めて、誰でも理解できて、誰でも仕組みがわかる」ように公開された、ということを意味します。ところが今は、それが失われつつあります。後ほど掘り下げます。
ビットコインが解決しようとする最大の問題の一つは、さまざまな「権威」によって引き起こされてきた中央集権化です。中には有益な権威もあるかもしれませんが、一般論として──たとえば現金で1万ドルを超えるものを買おうとしたことはありますか?おそらく、かなり難しいはずです。でも、スマホでビットコインの取引をすれば、はい、完了。誰にも聞かれません。
データと仲介の問題
スーパーに行って商品を買うとき、どんなデータが自分について保存されるか考えたことはありますか?多くの人は、いわゆる「トークン」(ここで言うトークンは暗号資産や草コインのことではなく、購買時のリワードトークンやポイントなどの意味です)を使います。あなたについてどんなデータが保存されるのでしょう?それは本当に必要でしょうか?
なぜ、あなたと僕の間に直接のやり取り──財やサービスの交換──があってはいけないのでしょう?それこそが、ビットコインが誰にでも提供するものです。だから存在しているのです。思い出してみてください。2008〜2009年、私たちは金融危機の最中にいました。ビットコインは、まるで火の中からよみがえった不死鳥のように誕生しました。誰も知らない新しいもので、みんな恐れていた。「どう動くの?なぜ使うの?」──でも、ホワイトペーパーを読めば理由がわかります。
ノード・トランザクション・マイニング
ビットコインを理解するうえで本質的な要素の一つが「マイニング」です。先ほども言ったように、こうしたカンファレンス(BTC Prague のような素晴らしい場でさえ)でも、マイニングの仕組みを教える人は多くありません。「マイニングは金持ちのやることで、メガワット級の電力設備があるから採掘できる。自分には無理だ」と思っている人もいるでしょう。でも、マイニングはもっと小さなところから始められます。この点は後で詳しく話します。
本題に入る前に、僕はビットコインを「三本柱の家」にたとえています。
1本目の柱はノードです。自宅やクラウドなどで動かすノードに、ブロックチェーン上のあらゆるデータが保存されます。
2本目の柱はトランザクション。財などを交換するために作られるものです。トランザクションはノードなしには作れませんし、ノードはトランザクションなしには存在意義を持ちません。両者は結びついています。
そして3本目の柱がマイニング。ネットワークに流れ込むトランザクションを「並べ替え」、ブロックという単位にまとめ、ネットワークに流します。私たち人間がブロックチェーンの動きを理解しやすいように整理してくれる役割です。
要するに、マイニングはトランザクションを組織化し、トランザクションは交換やデータ保存を可能にし、ノードはそれらを支えるデータベースです。どれか一つでも崩れたり汚染されたりすれば、システム全体が止まってしまう。未来はあなたが思うほど明るくないかもしれない──だからこそ重要なのです。
ハッシュレートの伸長と産業化
現状はどうでしょう。もしこのチャート(mempool.space というブロックチェーンの状況やブロックの保存状況、マイニングの推移が見られるサイトからのもの)を見たことがなければ、それはそれで問題ではありません。ここに示されているのは、ビットコイン誕生以来のハッシュレートの伸びです。興味深いのは、マイニングデバイスの増加と巨大施設の台頭が見て取れることです。
産業的マイニングは現実のものになりました。さきほど「マイニングは誰にとっても簡単ではない」と言いました。自宅の地下室やリビングの隣に大規模ファームを設置するのは無理ですし、ファンの轟音も聞きたくないでしょう。技術が進歩するにつれて、産業的マイニングも拡大してきました。巨大企業は「あなたのマシンをうちでホストします」と謳い、確かに魅力的です。でも、それはシステム全体に何をもたらすのでしょう?
マイナーの時間選好の変化と中央集権化リスク
近年、マイナーの性質は変わりつつあります。ハッシュレートが上がるにつれて、長期的な視点が失われ、「とにかく早く儲け、電力で損をしないこと」だけを考える傾向が強まりました。しかし先ほど述べたとおり、マイニングの柱が崩れれば家全体が崩れます。ハッシュレート以外にも重要な要素があるのです。
たとえばマイニングプール。今日は深掘りしませんが、プールは多数のデバイスのハッシュレートを束ね、次のブロックを見つけるための集合体です。いまやソロマイニング(単独)でブロックを当てるのは、1台や数台では極めて非現実的です。だからプールは存在します。でも、プールの中央集権化が進めば、時間とともにネットワークに問題を引き起こします。
ハードウェア進化と、その影
マイニングは CPU → GPU → FPGA → ASIC へと進化してきました。ASIC(特定用途向け集積回路)は「ひとつのことしかできないチップ」という意味ですが、悪いわけではありません。効率は上がり、消費電力は下がります。
しかし、ここで自問すべきは「正当性(レジティマシー)をどう担保するか」です。あなたがマイニング機器を買ったとして、その動作を理解していますか?その機械の中で何が起きているか知っていますか?
会場に質問です。「マイニングの仕組みを理解している」という方は手を挙げてみてください。……素晴らしい。1つの会場でこれほど多く手が挙がるのは初めてです。たいていはもっと少ない。実のところ、マイニング自体はそれほど複雑な作業ではありません。ただし、この分野で本当に必要なのは「オープンであること」「透明であること」「参加したいすべての人に知識を返すこと」です。知識があってこそ、三本柱は生き残れます。
企業を無批判に信頼していると、良くないことが起き得ます。2013年末から2014年にかけて、マイニングデバイスにバックドアが見つかった事例がありました。調査され、公表されるまで誰も気づかなかった。これは本当に恐ろしい話です。暗い時代が訪れないよう、システムを変えなければなりません。マイニングを誰にでも開かれたものにし、業界を再びオープンソースへと転換させ、皆が恩恵を受けられるようにする必要があります。
「Bitaxe(ビテックス)」という取り組み
DH Magazine Proへの招待
月7ドルでDH Magazine Proに参加して、より詳細な情報を受け取りつつ、Diamond Handsの活動を支援しよう!
詳細は以下のPro版の内容紹介記事をご確認ください。
Keep reading with a 7-day free trial
Subscribe to Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌 to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.